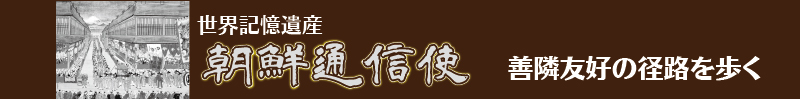掲載日 : [2020-06-26] 照会数 : 7001
朝鮮通信使 善隣友好の径路を歩く<43>ユネスコ登録と江戸城(終)
 [ 倭館跡(釜山・龍頭山) ]
[ 倭館跡(釜山・龍頭山) ] [ 江戸城跡(現・皇居、2019年) ]
[ 江戸城跡(現・皇居、2019年) ] [ 東菜府東軒(釜山) ]
[ 東菜府東軒(釜山) ]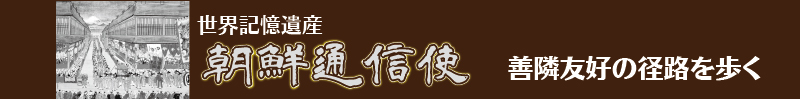
あらためて問われる「交隣堤醒」
盧泰愚元大統領が1990年に来日したとき、宮中晩餐会で「270年前、朝鮮との外交にたずさわった雨森芳洲は、『誠意と信義の交際』を信条としたと伝えられます。彼の相手役であった朝鮮の玄徳潤は、東莱に誠信堂を建て、日本の使節をもてなしました。今後の韓日関係もこのような相互尊重と理解の上に、共同の理想と価値を目指して発展するでありましょう」と述べている。
「平和の使節を〝世界の記憶〟に~朝鮮通信使 登録への道~」(NHK、2018年1月21日)が、放映された。朝鮮通信使がユネスコの「世界の記憶」に登録されるまでの過程が、日韓共同学術会議の録音に基づき編集されたドキュメントである。
両国の登録遺物への相違から会議が始まる。例えば「国書」について韓国側の意見は、朝鮮から日本に送られたものであって、それに値する同格の遺物が韓国には残っていない。これでは朝貢(使者が来て貢物を献上すること)使節に思われるのではないか。
その問いに対して日本側は、「国書」が朝鮮王朝に渡ったことを歴史的に裏付ける「通信使謄録」が残っており、「両国の国交は、信義の心をもって行う」と記されているとした。
韓国側の反論は、通信使を朝貢使だと考えてはいない。一般の人たちの認識として、日本が韓国を統治した時代に朝鮮通信使は「朝貢」であった、と見せかけたことがある。
両国の率直な意見が出され、外交文書としての「国書」と「謄録」の重要性を共有することで、申請する運びとなった。
だが、朝鮮通信使の橋渡し役をした対馬の藩主・宗義智の肖像画は、壬辰倭乱の道案内人としての認識が韓国人には強く、登録から除外された。
元号が「令和」へと変わった2019年の春。もし朝鮮通信使の存在が今日でも続いていたならば、東京(江戸)を訪れていたのでは? と思いながら、私は大手門を潜り江戸城跡に入った。権力の象徴とも言える大きな城の石垣の脇を通り本丸を望む。世界各国から来日した観光客が「乾通りの桜の通り抜け」に列をなしていた。
200余年も継続した両国の友好関係も、明治になると戦争が勃発。日本は朝鮮半島を統治した。「友好」とは、脆く壊れやすいものである。
両国の外交において複雑になってしまったこの時代にこそ、雨森芳洲の名著『交隣堤醒(こうりんていせい)』で唱えられている言葉「誠信の交わりという事は互いに欺かず争わず真実で交わることである」を、改めて問わなければならない。
(終わり)
藤本巧(写真作家)
2018年5月から連載してきた「朝鮮通信使善隣友好の径路を歩く」は今回で終了します。
(2020.06.25 民団新聞)