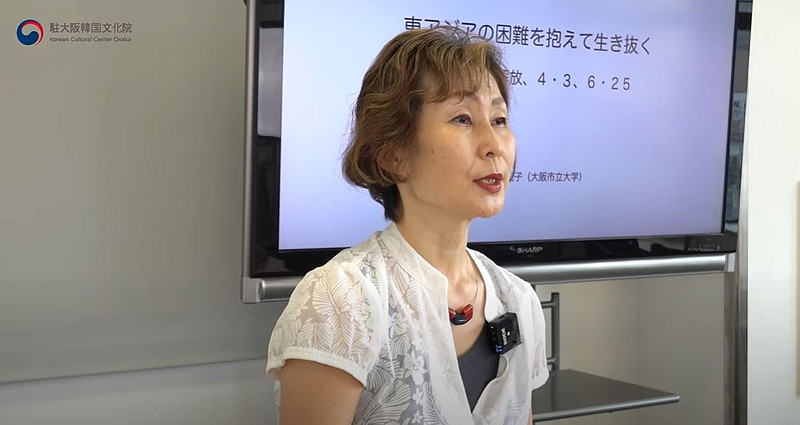掲載日 : [2020-07-08] 照会数 : 6955
済州島から阪神への 住民移動の背景説明
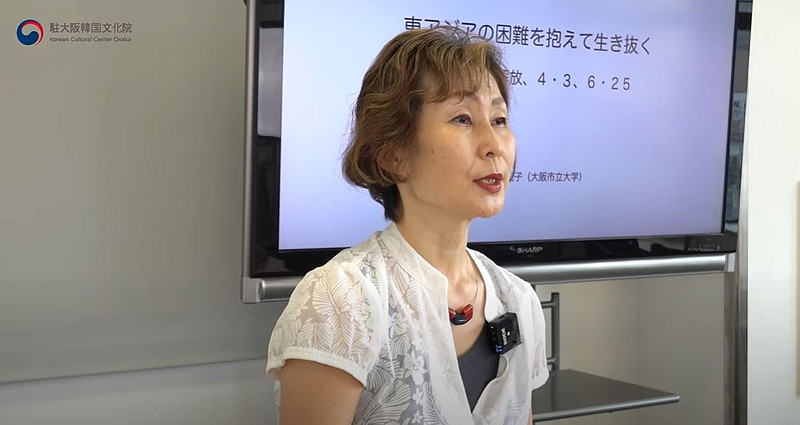 [ オンラインで講演する伊地知教授 ]
[ オンラインで講演する伊地知教授 ]
伊地知教授がオンライン講座 大阪韓国文化院
大阪韓国文化院(北区中崎)は、「韓国戦争70年」を迎えた先月、大阪市立大学の伊地知紀子教授を招いての特別オンライン講演会「東アジアの困難を抱えて生き抜く済州島民と解放、4・3、6・25」を開催した。
同講演会は3部構成。第1部は「日本の植民地支配と済州島」をテーマに、日本の植民地期に済州島から大阪に渡って来た人たちの歴史とその背景について紹介した。
伊地知教授は、大阪に済州島民が多く住んでいることに関心を持ったことから、実際に済州島の杏原村で暮らしながらフィールドワークを行ってきた。
また、1999年に結成した「在日済州島出身者の生活史を記録する会」でもインタビューを積み重ねてきた。
伊地知教授は1910年の韓国併合直後から18年にかけて、朝鮮総督府が行った土地調査事業に言及。これによって「多くの人たちが畑や田を失い、生活の糧を求めて移動しなければならない時代に入らざるを得なくなった」と指摘した。
日本では14年から起きた第一次世界大戦で多くの男性労働力が失われていた。済州島の場合は、その後、阪神が工業地帯になっていくなかで、安価な零細中小工場の労働力として多くの人たちが日本にやって来たという。「その流れを最も大きくした要因として、1923年の済州島と大阪の直行航路の開設があった」と説明した。
当時、済州島の人たちがどういう仕事に就いたかについて調査した地理学者、桝田一二さんの34年の統計によると、ゴム工場、機械工場、ガラス、ホーローといういずれも零細町工場であり、加えて海女というのもあると説明。
さらに伊地知教授は、大阪で話を聞いた済州島出身の女性が経験した、紡績工場での過酷な労働環境について語った。
また、「宮廷女官チャングムの誓い」の最終話のロケ地である松岳山陣地洞窟は、太平洋戦争末期に日本軍の人間魚雷を格納する洞窟跡であり、周辺の畑には日本軍の訓練機「赤とんぼ」の格納庫が今も33個残っていると説明した。
(2020.07.08 民団新聞)